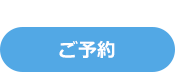院長のブログ
音楽が体に与える影響とは?
音楽が体に及ぼす影響は、単なる「気分がよくなる」だけでなく、神経系・内分泌系・免疫系など複数の生理的メカニズムに科学的に影響を与えることが分かっています。
「音楽が体に与える科学的影響」
① 自律神経系へ作用して交感神経(緊張)と副交感神経(リラックス)のバランスに働きかけます。ゆったりとしたテンポ(60〜80拍/分)の音楽は、副交感神経を優位にし、心拍数・血圧・呼吸数を下げてリラックス状態を誘導します。アップテンポの音楽は、交感神経を活性化し、覚醒・集中・運動パフォーマンスの向上を助けます。音楽を聴くことで心拍数が平均5〜10%低下することが、生理学的研究で報告されています。
② 音楽は脳内の報酬系を刺激し、以下のような脳内ホルモン(神経伝達物質)を分泌させます。
ドーパミン:好きな音楽で分泌が増加し、「やる気」や幸福感を高める。
セロトニン:穏やかな音楽でストレス緩和、うつ症状軽減に寄与
オキシトシン:合唱・共同演奏などで分泌、共感や絆を深める
エンドルフィン:激しい運動や感動的な音楽で分泌され、痛みの感受性が下がる
③ 脳波への影響
音楽は脳波にも影響を与え、集中・リラックス・睡眠などの状態に導くことができます。
α波:穏やかなBGMやヒーリング音楽で誘導されやすい。リラックスしたい時。
θ波:繰り返しのある音楽や自然音で誘導されやすい。瞑想したい時。
β波:テンポの速い音楽やアップビートな曲で促進。集中したい時。
④ 痛みの緩和(ゲートコントロール理論)
脊髄には「痛みの情報の入り口(ゲート)」があり、他の感覚(触覚や聴覚)でそのゲートを塞ぐことで、痛みの知覚を抑えることができるとする理論。
好みの音楽を聴くことによる聴覚刺激が痛み信号の「競合刺激」となり、脳に届く痛みの信号が弱まるといわれています。
⑤ 免疫系への影響
ストレスの軽減と自律神経バランスの正常化により、免疫機能が高まると考えられています。
唾液中のIgA(免疫グロブリンA)の増加が音楽聴取後に確認された研究があったり、血中のNK細胞活性(ナチュラルキラー細胞)も改善された例があるそうです。
⑥ 呼吸・筋緊張・内臓機能への影響
音楽のテンポに呼吸や筋活動が同調することがあり、これを「エンタレインメント(同調現象)」といいます。
呼吸:ゆっくりした音楽で自然と呼吸が深く、遅くなる。
筋肉:筋緊張が緩和され、マッサージや手技の効果が高まりやすくなる。
消化:副交感神経の活性化で消化機能が高まる。
★野毛整骨院の場所★
住所:神奈川県横浜市中区吉田町64-1
吉田町商店街の吉田町本通りにあります。老舗鶏肉専門店「梅や」さんの向い、ミニストップの隣です。
桜木町駅と関内駅、日ノ出町駅と馬車道駅を結んだちょうど真ん中、大岡川沿い都橋からすぐの場所です。
横浜市庁舎、伊勢佐木モールからも徒歩圏内です。
★交通事故治療★
当院では交通事故によるケガの治療も行っています。(自賠責保険)
交通事故によるトラブルについては「無料で相談できる弁護士さん」を紹介することも可能です。
お気軽にご相談ください。